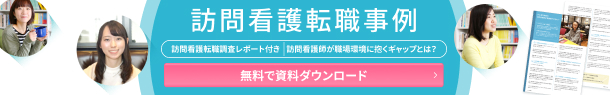看護師の育休明けに感じる不安とは?スムーズに復職するための働き方を解説

「もうすぐ育休から復帰だけど仕事と育児の両立が不安」「ブランクでスキルや知識が遅れていないか心配」
看護師の仕事は、患者さまの命にかかわる責任の重さから緊張感が伴います。そこに育児の役割が加わり、仕事との両立に不安を感じている方は少なくありません。
この記事では、育休明けを控えた看護師が抱きやすい不安や悩みとその対処法、無理なく復職するための準備について解説します。スムーズに職場に戻り、家庭と仕事のバランスを取りながら、自分らしく働き続けるためのヒントを見つけましょう。

看護師が育休明けに感じやすい不安
育休復帰を控えた看護師が感じる不安は、職場復帰への懸念や、育児と仕事の両立にかかわる問題にわけられます。
- ブランクでスキルが不足している
- 復帰後の人間関係に馴染めない
- 希望する部署に配属されない
- 子どもの急な体調不良で仕事ができない
- 仕事と家事・育児を両立できるか心配である
これらを事前に知り、対策を立てることで、心にゆとりを持って仕事と育児に取り組めるでしょう。

ブランクでスキルが不足している
長期間のブランクで「自分の知識やスキルが古くなっているのではないか」と不安を感じる看護師は多くいます。
とくに、集中治療室や手術室など専門性が高い部署にいた方は、急変対応や機器の操作について「すぐに思い出して対応できるだろうか」という強い焦燥感を抱きがちです。

復帰後の人間関係に馴染めない
育休中に看護師の入れ替わりがあり、職場の雰囲気に馴染めないのではないかという不安も多く聞かれます。
仲良かった同僚が退職したり、自分以外の職員同士で新しいグループが形成されていたりすると、復帰後に孤立感を抱きやすくなります。また、後輩看護師がリーダー業務や指導係を担っている場合、以前との立場の違いから接し方に戸惑うこともあるでしょう。

希望する部署に配属されない
育休に入る前の部署を希望しても叶わないかもしれません。体力的な負担が少ない部署や残業が少ない部署を希望しても、人員配置の都合により、希望と異なる部署になる可能性もあります。
たとえば、残業の多い救急外来やオペ室など、子育て中の生活リズムと合わない部署に配属されると、仕事と家庭の両立が難しくなるのではないかと心配する声もあります。

子どもの急な体調不良で仕事ができない
育休復帰を控える看護師が感じる不安は、子どもの急な発熱や病気で欠勤・早退せざるを得ないときの対応です。看護師は欠員が出るとほかのスタッフに負担がかかるため、休むことへの罪悪感を抱きやすいからです。
小さな子どもは感染症をもらうことが多く、保育園からの呼び出しや看病で連日休みを取る必要が生じます。「職場で迷惑がられているのではないか」という精神的なプレッシャーが大きなストレスになります。

仕事と家事・育児を両立できるか心配である
育休復帰を控える看護師には、仕事と子どもの世話や家庭生活を回せるかという気がかりがあります。育休前と違い、子育てに多くの時間と労力が割かれるため、限られた時間で仕事・家事・育児をこなせるかという不安がプレッシャーになりがちです。
厚生労働省「看護師等(看護職員)の確保を巡る状況」によると、看護職員が子育てを理由に離職するケースは30代で14.5%、40代で16.1%と高くなっています。
これは、子どもの送迎や体調管理といった子育てと仕事を両立できず「子どもに十分なケアができないのではないか」と心配した結果、離職する看護師が少なくないことをあらわしています。

育休明けの看護師がスムーズに復職するための準備チェックリスト
育休明けの不安を解消し、スムーズに職場復帰するためには準備が重要です。
- 保育園・幼稚園を確保する
- 家族との役割分担を確認する
- 職場との面談で勤務希望や配属先を相談する
- 育休明けまでに配属先の知識やスキルを勉強する
- 職場の復帰支援プログラムを活用する
これらのチェックリストに沿って準備を進めることで、不安を解消し、自信を持って職場に戻れるでしょう。

保育園・幼稚園を確保する
復職のタイミングに合わせて、子どもの預け先を確保することが大切です。保育園や幼稚園の入園手続きには時間がかかり、すぐに入れないケースも多いため、入園決定が復職直前になると、職場への復帰日を確定できず、人員配置の調整が滞ってしまうからです。次のポイントをチェックして、早めに複数の施設に申し込みましょう。
- 自宅や職場からの距離
- 開所時間
- 病児保育の有無
預け先の確保は復職後の生活に欠かせないため、なるべく早い時期から準備を始めましょう。

家族との役割分担を確認する
復職前に、夫や家族と家事・育児の分担について話し合い、協力体制を築きましょう。看護師の仕事と家事・育児を1人でこなすのは難しく、パートナーと協力することが心身の安定に不可欠です。
朝の送迎や夕食の準備、子どもの体調不良時の対応などの役割分担を決めることで、復帰後のストレスを減らせます。祖父母が近くにいる場合は、送迎や緊急時のサポートなど、どのくらい手伝ってもらえるのかを確認しておくことをおすすめします。

職場との面談で勤務希望や配属先を相談する
復帰前に看護師長や人事担当者と面談し、勤務形態や配属先の希望をはっきりと伝えましょう。次のように伝えることで、病院側も配慮しやすくなり、ミスマッチによる早期離職を防げます。
- 9時から16時までの時短勤務を希望する
- 救急外来やオペ室など残業の多い部署以外を希望する
- 子どもが小学生に上がるまでの間、夜勤免除を希望する
自分の希望と職場のニーズをすり合わせるための重要な機会であるため、面談前に希望や条件をまとめておきましょう。

育休明けまでに配属先の知識やスキルを勉強する
復職後に看護師が不安にならないように、育休中に配属予定の部署の知識やスキルを確認しておくことが重要です。ブランクへの不安が和らぎ、自信を持って働けるようになるからです。取り組み例は次のとおりです。
- 最新のガイドラインを確認する
- オンライン研修を受講する
- 知り合いからマニュアルを借りて目を通す
ブランクを埋めるための知識のアップデートは、心理的な安定を得るための準備となります。焦らず、自分のペースで取り組みましょう。

職場の復帰支援プログラムを活用する
職場の復職支援プログラムや研修があれば、積極的に活用しましょう。
復帰支援プログラムは、ブランクのある看護師が現場の最新情報を知り、技術を再確認できるため不安解消に役立ちます。
また、ナースセンターの「復職支援研修・実習」や「ナースカフェ」などの利用もスムーズに復職するために有効です。
関連記事:看護師は育休を取れない?給料とボーナス、復帰後の不安を減らすコツ3つ

育休明け看護師のリアルな働き方3パターン
育休復帰を控える看護師が選ぶおもな働き方は、大きくわけて次の3パターンです。
- 時短勤務で育休前の職場に復帰する
- 夜勤免除で働く
- 転職する
家庭の状況やキャリアの目標に合わせて、心身に無理のない働き方を選ぶことが、看護師を続けるために大切です。

時短勤務で育休前の職場に復帰する
復帰後の仕事と育児の両立を優先したい看護師に、よく選ばれているのが時短勤務です。
子どもが3歳未満の場合、育児・介護休業法にもとづいた時短制度を利用できるため、勤務時間を短縮でき、子どものお迎えに間に合わせやすくなります。たとえば、9時から16時までの勤務とすることで、子どもの生活リズムを崩さずに働けるでしょう。
関連記事:看護師の時短勤務とは?メリットデメリットや注意点などを解説

夜勤免除で働く
夜勤免除の働き方は、体力的・精神的な負担が減り、生活リズムが安定しやすくなります。
これは、育児介護休業法(第十九条)によって定められた権利です。看護師が希望した場合、小学生になるまでの間、深夜(午後10時から午前5時まで)の業務が免除されると規定されています。
夜勤手当は大きな収入源ですが、不規則な生活が看護師の心身に負担をかけ、子育て中の急な対応が難しくなります。そのため、生活の安定を優先して夜勤免除を選択する看護師が多いようです。

転職する
今の職場の制度や子育てへの理解度に不安がある、またはワークライフバランスを重視したい場合、転職を検討すべきです。環境を変えることが、長期的なキャリアの継続につながるからです。
ただし、育休を取得した後の退職には、いくつかの注意点があります。もらえる手当や給付金の問題が生じるほか、業務の引き継ぎや人間関係などでトラブルになる可能性があります。また、保育園を退園しなければならないリスクや、再就職のハードルが高くなることもあります。
トラブルを避けるためにも、まずは看護師長や人事担当者に相談したうえで、慎重に話を進めましょう。

育休明けで転職を考える看護師へ|失敗しない求人の探し方
育休明けの転職を成功させるには「子育てへの理解度」を優先して求人を探すことが重要です。
- 「子育ての理解がある」「ママ看護師が多数在籍している」などの職場を選ぶ
- 保育施設がある職場を選ぶ
- 夜勤免除や時短制度をチェックする
これらのポイントをしっかり確認することで、入職後のギャップを防ぎ、子育てと両立できる職場を見つけられます。

「子育ての理解がある」「ママ看護師が多数在籍している」などの職場を選ぶ
求人情報や職場のデータから、子育てに理解がある職場を選びましょう。ママ看護師が多い職場は、お互いの状況に理解があるため、急な欠勤や早退が発生しても協力しやすい環境が整っている可能性が高いからです。
- ママ看護師の比率
- 育休復帰率
- 平均残業時間
これらのデータをリサーチして働きやすさを判断しましょう。とくに、育休復帰率の高さは、職場の制度が整っている目安になります。

保育施設がある職場を選ぶ
院内に保育施設が併設されている職場は、育休明けの看護師におすすめです。
子どもと同じ施設内にいられる安心感があり、送迎時間の短縮になるだけでなく、子どもの急な発熱や体調不良時にもすぐに駆けつけられるというメリットがあります。
保育施設の開所時間や延長保育の有無などを確認し、自分の勤務時間とライフスタイルに合うかを見極めましょう。

夜勤免除や時短制度をチェックする
求人情報で、夜勤免除や時短勤務の制度が利用されているかをチェックしましょう。
制度があっても職場の雰囲気で利用できない場合があるため、実際にどのくらいの看護師が活用できているかに注意が必要です。
「夜勤免除で働いているスタッフの割合」や「時短勤務が何歳まで可能か」など、具体的な運用状況を採用担当者や病院のホームページで確認し、制度が機能している職場を選びましょう。

求人情報だけでなく口コミや実際の声を確認する
職場の本当の雰囲気を知るために、口コミや実際の声も確認することが大切です。
求人情報には良い面ばかりが強調されがちですが、残業の実態や人間関係のリアルな事情などは、実際に働いている人の声でしかわかりません。
病院見学や採用の面接の際に「子育て中のスタッフが働きやすいか」を質問したり、看護師の口コミサイトを利用したりして情報を集めましょう。

育休明けにおすすめの職場
仕事と育児が両立しやすく、復帰後の負担が少ない職場を紹介します。
- 総合病院
- クリニック
- 訪問看護ステーション
これらの職場は、勤務時間の柔軟性や残業の少なさなど、子育て中の看護師にとってメリットがあるため、復帰後の選択肢として検討してみましょう。

総合病院
総合病院は、育休前のスキルを活かし、キャリアを継続したい看護師におすすめです。
大規模な総合病院には、夜勤免除や時短勤務などの制度が整っている場合が多く、復職支援プログラムも充実している傾向があります。また、多様な部署があるため、体力的な負担が少ない部署への配属を相談しやすい点もメリットです。
給与や福利厚生が安定しており、院内保育所が併設されていることも多く、子どもの急な発熱時にも対応しやすいため、復帰後の安心感につながります。

クリニック
外来診療のみのクリニックは、決まった時間に退勤しやすく、育児との両立がしやすい職場です。夜勤がなく、残業も少ない傾向にあるため、生活リズムが安定します。さらに、土日祝日が休診の場合は、家族との時間も確保しやすいメリットがあります。
小児科や皮膚科など、専門性を絞ったクリニックを選べば、業務範囲が限定されるため、ブランクがあっても業務に早く慣れやすいという点も魅力です。

訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、勤務形態の柔軟性が高く、育児との両立を目指す看護師におすすめの職場です。
職場によっては直行直帰が可能で、オンコールを免除してもらえる場合もあります。病院勤務と比べて、医療処置をおこなう頻度も少ないため、ブランクによる手技への不安を感じにくいでしょう。
また、訪問時間が決まっており「9時から16時まで」と勤務時間を区切りやすいため、保育園のお迎えに間に合いやすく、急な残業で予定が崩れにくいのが特徴です。家庭の事情に合わせた柔軟な働き方を実現しやすいというメリットがあります。

先輩ママ看護師の声
実際に育休復帰後の働き方を工夫した先輩ママ看護師の事例を紹介します。
- 事例1:時短勤務でも周囲の理解があり復帰できた
- 事例2:保育施設があると急な呼び出しがあっても安心できた
- 事例3:転職して夜勤なしにして正解だった
これらの事例を参考に、不安を解消し、キャリアと家庭に合った働き方を見つけるためのヒントにしてください。

事例1:時短勤務でも周囲の理解があり復帰できた
| Aさん(30代・総合病院勤務)は、育休から復帰する前は「時短勤務で働くと迷惑をかけるかもしれない」という気持ちが強かったため、看護師長に相談したうえで時短勤務を利用しました。部署には同じように子育て中のママさんが多く、急な早退でも「お互い様だよ」と協力し合える環境でした。周囲の理解のおかげで、罪悪感なく子どもとの時間を大切にしながら働くことができています。 |
時短勤務制度の活用に加え、子育て中のスタッフが多い部署を選ぶことで、精神的な負担が大幅に軽減されます。

事例2:保育施設があると急な呼び出しがあっても安心できた
| Bさん(40代・託児所つきの病院勤務)は、子どもが体調を崩しやすいことが気がかりでした。しかし、病院内に24時間対応の託児所があったため安心して復帰できました。託児所から連絡が来てすぐに様子を見に行けます。また、送迎時間もかからず、その分残業が少し長引いてもカバーできました。 |
院内託児所があると、緊急時の対応と送迎の負担を減らせます。この距離の近さが、仕事中の安心感と時間的なゆとりを生み出します。

事例3:転職して夜勤なしにして正解だった
| Cさん(30代・クリニック勤務)は、以前の病院は残業と夜勤が多く、家庭がうまくいかなくなると思い、夜勤なしのクリニックに転職しました。給与は減りましたが、ワークライフバランスを優先したことで心にゆとりが生まれました。子どもとゆっくり夕食を食べられるようになり、家族全員が笑顔になりました。自分の健康と幸せを優先して正解でした。 |
育児との両立には、働き方の環境を根本的に変える必要があります。夜勤・残業がない職場に転職することで、心身の健康と家庭の安定を取り戻せる可能性があります。

育休明けの看護師についてのよくある質問
育休明けの看護師についてよくある質問に回答します。

Q1:育休明けの看護師は、いつから復職する人が多いですか?
多くの看護師は、子どもが1歳になるタイミングで復職します。
原則として、子どもが1歳になるまで育児休業を取得できるため、この時期を区切りとするからです。また、保育園の入園募集は4月が多くなるため、4月に合わせて復職できるよう調整するケースもあります。

Q2:育休明けすぐに看護師を辞めても良いですか?
育休明けですぐに退職しても法的な問題はありませんが、職場への影響もあるため、誠実な対応を心がけましょう。
復帰後に家庭の事情で働くことが難しい場合は、退職の意思をなるべく早く伝え、円満退職を目指すことが大切です。

Q3:育休明けで復帰するときはいつあいさつに行けば良いですか?
育休明けのあいさつは、復帰の1〜2週間前に訪問してあいさつをするか、当日の朝に簡単に済ませるのが一般的です。
復帰直前にあいさつすることで、職場の現状を把握し、顔と名前を再確認できます。「〇日からお世話になります。よろしくお願いいたします」と看護師長や同僚にあいさつし、育休や時短勤務などの配慮への感謝を伝えましょう。

育休明けの看護師は無理せず、自分と家族を大切にできる働き方を選ぼう!
看護師として責任感が強いからこそ、育休復帰を前に「完璧にこなさなければ」と無理をしがちです。しかし、心身が健康でなくなると、患者さまのケアや育児が難しくなる場合もあります。
育休明けは「自分と家族を大切にできる働き方」を選ぶことが重要です。今の職場で両立が難しいと感じたら、子育て支援が充実した新しい職場を探すことも有効な解決策といえます。
NsPaceCareerは、訪問看護に特化した求人サイトであり、生活状況や希望に寄り添い、育児への理解がある職場を紹介しています。無理なく、看護師として活躍できる場所を見つけましょう。
<参考サイト・文献>
 NsPace Careerナビ 編集部
NsPace Careerナビ 編集部 「NsPace Career ナビ」は、訪問看護ステーションへの転職に特化した求人サイト「NsPace Career」が運営するメディアです。訪問看護業界へのキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。