看護師が無駄だと感じる業務とは?業務改善の進め方と3つの事例を紹介
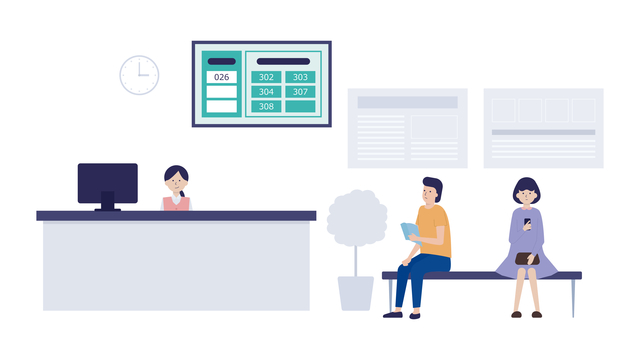
「日々の業務に追われて、患者さまと向き合う時間が減っている」「もっと効率的に働きたいけれど、何から手をつければ良いかわからない」
このように、無駄な業務に時間を取られていることに悩む看護師は多いのではないでしょうか。本来の看護業務に集中できない状況は、仕事のやりがいを失うだけでなく、患者さまのケアの質にも影響を与えかねません。
この記事では、看護師が無駄だと感じる業務の具体例と、業務改善の進め方について詳しく解説します。無駄な業務を見直し、患者さまのケアに集中できる環境づくりに役立ててください。

看護師が無駄だと感じる業務
看護師の業務には、目的がはっきりしていなければ無駄になってしまうものがあります。
- 前残業での情報収集
- 目的がはっきりしない会議
- 強制的に参加しなければならない研修
- 業務が終わってからの先輩や同僚待ち
これらの業務は、昔からの習慣で続いているだけで、看護師がやるべき仕事に集中する時間を奪うリスクがあります。自分の時間を守るためにも、無駄な仕事を見つけて、改善策を考えることが大切です。

前残業での情報収集
前残業での情報収集は、看護師が無駄と感じてしまう業務の1つです。
早い人だと定時の1時間以上前から情報収集を始めたり、日勤から夜勤への申し送りで聞けばわかる内容を、時間をかけて電子カルテで確認している場合もあります。
情報収集は患者さまへの適切なケアには欠かせない業務ですが、非効率的な方法でおこなうと無駄な時間につながります。

目的がはっきりしない会議
会議の目的があいまいであれば、参加者が何を話し合うべきかわからず、結論が出ないまま時間だけが過ぎてしまうため、無駄な業務になる可能性があります。
たとえば、毎回同じ内容を報告して、具体的な改善策が話し合われずに終了する定例会議が挙げられます。とくに、勤務時間外の参加を求められるような会議は、看護師の心身の負担を大きくしがちです。
会議の目的とゴールを事前に共有しておかなければ、ただ時間が過ぎるだけの無駄な業務になってしまいます。

強制的に参加しなければならない研修
強制的に参加しなければならない研修も、無駄な業務になりやすいです。
一例として、新卒者に専門性が高い研修や、すでに知っている内容を繰り返す研修などは、理解や成長につながらないだけでなく、モチベーションの低下を招くこともあります。
看護師のスキルや興味に合わせた研修でなければ、無駄な時間だと感じてしまうでしょう。

業務が終わってからの先輩や同僚待ち
業務終了後に、ほかのメンバーが退勤するまで待つ風習は、無駄な業務の典型例です。
記録が終わっていても先輩が残っているから帰りづらい、といった心理的圧力が働くケースが挙げられます。
自分の業務が終わってもすぐに帰れない状況は、ワークライフバランスの実現を阻害する無駄な時間となるかもしれません。

看護師が無駄な業務を減らす必要がある理由
看護師の無駄な業務を放っておくと、病院の運営や、看護師の働き方に悪影響を与えてしまいます。ここでは、無駄な業務を減らす必要がある理由を解説します。

人手不足の深刻化
無駄な業務の多さは、看護師の離職につながり、人手不足を深刻化させる恐れがあります。
厚生労働省「看護師等(看護職員)の確保を巡る状況」によると、看護師・准看護師の有効求人倍率は2.20倍と高く、人手不足の状況が続いています。業務負担が大きくなることで、看護師の心身の負担が増え、ストレスが強くなりがちです。
たとえば、無駄な業務に追われ、残業が当たり前になっている職場では、ワークライフバランスを保つのが難しくなり、離職を考える看護師が増えてしまいます。
無駄な業務を減らすことは、働きやすい環境づくりにつながり、人手不足の解消に役立つはずです。

看護師の業務量の増加
無駄な業務が多いと、看護師の業務量が増加してしまいます。
医療技術の進歩や在院日数の短縮に加えて、近年の働き方改革により、看護師に求められる役割が拡大し、業務内容が複雑化しています。実際に、次の表のように業務の効率化を進めている病院は多い傾向です。
| 項目 | 「実施している」と回答した病院の割合 |
| 業務の標準化 | 75.9% |
| 多職種との連携、タスク・シフト/シェア | 53.1% |
| 勤務体制の整備 | 51.2% |
| 帳票類の整理 | 48.6% |
| ICTを用いた情報の共有 | 39.8% |
無駄な業務に時間を取られると、本来のケアに集中できなくなるため、業務の効率化はケアの質を維持するために不可欠です。
関連記事:看護師の働き方改革とは?ワークライフバランス実現への取り組み5つと事例

看護師が無駄な業務を減らすための業務改善の進め方
無駄な業務を減らすためには、効果的な業務改善の進め方を知っておくことが大切です。ここでは、具体的な5つのステップを解説します。
- 業務の見える化とタスク整理
- スタッフ同士の意見交換とアンケートの実施
- 看護補助者やクラークとの役割分担の見直し
- 業務マニュアルの整備
- 業務改善を実施した後の評価
これらのステップを順番に進めることで、無駄な業務を根本から見つけ出し、効率的な働き方を実現できます。チーム全体で協力することが成功のカギとなります。

1.業務の見える化とタスク整理
業務の見える化とタスク整理は、無駄な業務を削減するための第一歩です。
1日の看護師の業務を時間ごとに書き出し、それぞれの業務にかかる時間を記録してみると「この業務にこれだけ時間がかかっていたのか」と気づけ、改善点を見つけやすくなります。

2.スタッフ同士の意見交換とアンケートの実施
スタッフ同士で意見交換をおこなったり、アンケートを実施したりすることも、業務改善を進めるうえで大切です。
たとえば、勤務シフトごとに「無駄だと感じる業務」や「改善してほしいこと」を話し合う場を設けてアンケートを実施するのも1つの方法です。
スタッフ全員が改善に参加することで、より良いアイデアが生まれやすくなります。

3.看護補助者やクラークとの役割分担の見直し
看護補助者やクラークとの役割分担を見直すことは、看護師の業務負担を減らす効果的な方法です。
たとえば、次の業務を看護補助者やクラークに任せることで、看護師はバイタルサインのチェックや医療処置といった本来の業務に専念できます。
- 物品の補充
- 環境整備
- 患者さまの食事準備
- 受付の応対
このように、職種ごとの役割を明確にすることで、チーム全体の業務が効率化されます。ただし、業務を一方的に押しつけてしまうと、看護補助者やクラークの働き方に大きく影響する可能性があるため、お互いに配慮する姿勢が大切です。

4.業務マニュアルの整備
業務マニュアルの整備は、無駄な業務を減らし、業務の質を安定させます。というのも、業務の進め方が標準化されていないと、人によってやり方が異なり、無駄な作業が発生しやすいためです。
申し送りの際に伝える情報の内容や、記録方法のフォーマットを統一することで、情報共有の時間が短縮されます。
また、退院支援の手順をマニュアル化することで、看護師がスムーズに手続きを進められ、患者さまやご家族への説明漏れを防ぐことにもつながります。

5.業務改善を実施した後の評価
業務改善を実施した後は、必ず評価をおこないましょう。改善策が本当に効果的であったのかどうかを検証しなければ、次の改善につながらないためです。
具体例として、新しいマニュアルを導入した1ヶ月後にアンケートを実施し、記録時間の短縮や業務負担の軽減についての効果を検討してみましょう。
評価と改善を繰り返すことで、無駄な業務を継続的に減らせます。

看護師の業務改善の具体例
ここでは、実際に業務改善に成功した病院の具体的な事例を3つ紹介します。

病棟で看護補助者との業務分担を見直して無駄な業務を削減
| 看護師が物品補充やベッドメイキングなどの業務に追われている状況でした。看護補助者と看護師が話し合い、それぞれの役割を見直しました。看護補助者が中心となって物品管理や環境整備をおこなうようにした結果、看護師はバイタルチェックや医療処置などの業務に集中できるようになり、残業時間の削減にもつながりました。 |
タスク・シフト/シェアを進めることで、看護師の専門性を活かす働き方が実現しました。看護補助者の業務範囲をはっきりさせることが、成功のカギといえるでしょう。

病棟で入退院のオリエンテーションを動画で実施して時間を短縮
| 入退院が多く、看護師が患者さまやご家族にその都度、説明することが負担になっていました。そこで、病棟のルールや入院生活の注意点をまとめた動画を作成し、患者さまに視聴してもらい、わからないことを看護師に確認してもらうようにしました。説明の時間が短縮され、患者さまからの質問にもスムーズに対応できるようになりました。 |
デジタルツールの活用によって、看護師の業務負担を軽減できた好例です。動画を活用すれば、説明の質を均一に保ちながら、時間を有効に使えるようになります。バイタルサインのデータ入力やナースコールの対応など、看護業務のDX化(デジタル技術を活用して業務を効率化する仕組み)により、業務改善を進められるでしょう。

外来での物品補充を曜日ごとの当番制にして無駄な業務を改善
| 外来では、物品が不足するたびに看護師が補充をおこなっていました。これにより、業務が中断されることが多く、無駄な時間が発生していました。そこで、物品補充を曜日ごとに担当者を決める当番制にしました。これにより、看護師がいつ補充すれば良いか明らかになり、業務の中断が減り、効率的に仕事を進められるようになりました。 |
この事例では、業務の標準化と担当者の明確化により、無駄な動きをなくすことに成功しています。簡単な工夫でも、チーム全体で取り組むことで改善につながることがわかります。
関連記事:看護師が効率よく動く7つのコツ!難しいときの対処法も解説

看護師の無駄な業務が多い職場の特徴と見極め方
無駄な業務が多い職場には、いくつかの共通した特徴があります。ここでは、そのような職場の見極め方を解説します。
- 看護師の離職率が高い
- 業務フローの見直しがされていない
- 看護師と看護補助者の役割分担がはっきりしない
- 業務改善に消極的な風土である
これらの特徴は、業務が非効率的で看護師に負担がかかっているサインです。就職や転職を検討する際には、これらの点に注目して職場環境を見極めることが大切です。

看護師の離職率が高い
看護師の離職率が高い職場は、無駄な業務が多い可能性があります。
無駄な業務が多いほど、看護師の心身の負担が増加し、仕事への不満が溜まりやすくなります。たとえば、慢性的に人手不足であり、長時間労働が当たり前になっている病院では、無駄な業務が放置されていることも少なくありません。
日本看護協会「2023年 病院看護実態調査」によると、正規雇用看護職員の離職率は11.8%であるため、転職先を決める際にはこの数値を基準にすると良いでしょう。

業務フローの見直しがされていない
業務フローの見直しがされていない職場は、無駄な業務が多いかもしれません。「昔からこのやり方だから」という慣例や前例主義が根強い可能性があるからです。
電子カルテが導入されているのに、手書きの記録も並行しておこなっていたり、非効率な情報共有の方法が続いていたりする職場もあります。
業務フローの見直しがされていない職場は、無駄な業務が残りがちです。

看護師と看護補助者の役割分担がはっきりしない
看護師と看護補助者の役割分担がはっきりしない職場も、無駄な業務が多い可能性があります。
それぞれの職種が何をどこまで担当するのかがはっきりしないため、看護師が本来おこなわなくても良い業務を担っていることがあるためです。
実際に、看護補助者がいるにもかかわらず、看護師が環境整備や物品補充をおこなっている病院や施設もあります。役割分担がはっきりしないと、業務の重複や非効率化につながります。

業務改善に消極的な風土である
新しいやり方を試すことに抵抗があったり、変化を嫌ったりする文化がある病院では、無駄な業務が多いかもしれません。
たとえば「忙しいから新しいことはできない」という理由で、スタッフからの改善提案が却下されてしまう職場が挙げられます。
業務改善に前向きに取り組む姿勢がなければ、無駄な業務はいつまでも減らないでしょう。

看護師が無駄な業務に疲れたときの選択肢
日々の無駄な業務に疲れてしまったとき、1人で抱え込まずにできることがあります。ここでは、2つの選択肢を紹介します。

異動を申し出る
部署異動を申し出ることは、無駄な業務に疲れたときの有効な選択肢です。
部署が変わることで業務内容や環境が変わり、気持ちをリセットできるためです。具体的には、忙しい急性期病棟から、比較的落ち着いた療養病棟へ異動することで、業務負担が減り、本来の看護に集中できるかもしれません。

転職を検討する
職場の風土そのものが変わらない場合は、転職を検討することも1つの選択肢です。
無駄な業務を削減することに積極的な病院や、看護師の働き方を尊重している病院はほかにも多くあるためです。求人サイトを活用すれば、業務改善に力を入れている病院や、効率的な働き方を推進している施設を見つけやすくなります。
とくに、訪問看護の分野に興味がある方は、訪問看護に特化した求人サイト「NsPaceCareer」を利用して、効率的に転職活動を進めてみてはいかがでしょうか。あなたに合った職場を見つけて、やりがいのある看護師生活を送りましょう。

看護師の無駄な業務についてのよくある質問
ここでは、看護師の無駄な業務についてのよくある質問にお答えします。

Q1:業務改善を提案しても聞き入れてもらえないときはどうすれば良いですか?
業務改善を提案しても聞き入れてもらえない場合は、具体的なデータやメリットを提示することが大切です。
たとえば「この業務を変更することで、月に〇時間の業務削減が見込める」のように、客観的な数値を示すと説得力が増します。また、個人的な意見としてではなく、チーム全体の問題として提起することも重要です。

Q2:業務マニュアルを作成する際のポイントは何ですか?
業務マニュアルを作成する際のポイントは、誰が見てもわかりやすい内容にすることです。
専門用語は避け、簡潔な言葉で説明し、写真やイラストを効果的に活用しましょう。また、一度作成したら終わりではなく、定期的に内容を見直し、改善を続けることが重要です。

無駄な業務を減らして看護師本来の仕事に集中しましょう!
無駄な業務を放置しておくと、看護師の心身の負担が増え、患者さまのケアの質にも影響を与えかねません。
ICT活用や役割分担の見直しなど、できることから少しずつ業務改善に取り組むことで、無駄な時間を減らせます。
看護師本来の仕事に集中できる環境を整え、やりがいのある看護師生活を送りましょう。
<参考サイト・文献>
 NsPace Careerナビ 編集部
NsPace Careerナビ 編集部 「NsPace Career ナビ」は、訪問看護ステーションへの転職に特化した求人サイト「NsPace Career」が運営するメディアです。訪問看護業界へのキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。


















