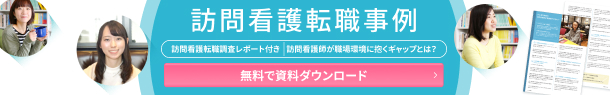看護師は子育て中でも夜勤をするの?両立する方法4つと免除制度を解説

「子どもが小さいうちは夜勤を避けたいけど、やらなきゃいけないの?」「子育てに家事に夜勤、体力的にきつい」
子育てと看護師の仕事の両立を考えるなかで、このように悩む方もいるでしょう。
法律や病院の制度によって夜勤が免除される可能性がありますが、夜勤をしなければならない場合は、負担を軽減する工夫がなければ、両立は難しくなります。
この記事では、子育て中で夜勤を免除してもらえる制度や、子育てと夜勤を両立するための方法、夜勤なしで働ける職場を紹介します。子育てをしながら夜勤をしているものの、つらさを感じている看護師は、自分や家族のために無理のない働き方を選ぶヒントとして参考にしてください。

看護師の子育て中の夜勤は必須ではない
育休から復帰を考える際、まず知っておきたいのが「夜勤制限」です。この制度を活用すると、子育て中の看護師は夜勤をしなくて済む可能性があります。

育児・介護休業法による「夜勤制限」
育児・介護休業法の第十九条では「小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、事業主は午後10時〜午前5時の就業を免除するように努めなければならない」とされています。つまり、子どもが小学校に入学するまでは、夜勤の免除が期待できます。
ただし、次のような看護師は夜勤免除の対象外になることもあるため注意が必要です。
- 雇用期間が1年未満である
- 深夜、子どもを保育できる同居の家族がいる
- 1週間の労働日数が2日以下である
- 労働時間がすべて深夜である
夜勤の免除や回数の調整については病院や施設によって異なるため、まずは上司や人事担当に相談してみましょう。

病院ごとの就業規則
病院によっては、育児中の職員を支えるために、夜勤免除の制度を独自に設けていることがあります。
たとえば「未就学児がいる職員は夜勤免除」「就学児童がいる職員の夜勤回数は月2回まで」など、子育て中でも働きやすいようにしている病院もあるようです。
ただし、すべての病院にこのような制度があるとは限りません。勤務先の就業規則を確認し、わからないことは人事課に相談しましょう。

看護師で子育てと夜勤の両立が難しい理由
看護師で子育てと夜勤を両立するときに、看護師が直面する困難や悩みは多岐にわたります。ここでは、両立が難しい理由を詳しく解説します。
- 夜間子どもを預ける場所がない
- 体調が崩れやすい
- 夜間に子どもを預ける罪悪感がある
- パートナーの協力を得られない
- 迷惑をかけまいと無理な働き方をしてしまう
具体的な悩みを知ると、適切な対策を立てるヒントが見つかるでしょう。

夜間子どもを預ける場所がない
子育てと夜勤を両立するうえで、多くの看護師が直面するのが子どもを預ける場所の確保という課題です。
夜間保育に対応した認可保育園や幼稚園は、ごく一部の地域に限られ、定員も少ないため、預け先を見つけるのは簡単ではありません。
パートナーや祖父母の助けがない家庭では、とくに夜勤をするのは難しいでしょう。

体調が崩れやすい
夜勤は身体のリズムが乱れやすく疲れもたまりやすいため、育児と両立している看護師は体調を崩しがちです。
十分な睡眠が取れないまま朝を迎えてしまうと、体調が万全ではないなかで家事や育児をこなさなければなりません。こうした状態が続くと、ストレスがたまりやすく仕事への意欲も低下しがちです。
無理を続けると、さらに日常生活や仕事がうまく回らなくなり、悪循環に陥る場合もあります。

夜間に子どもを預ける罪悪感がある
子どもを預けられた場合でも、夜に母親がそばにいないと、子どもが寂しがったり、夜泣きしたりすることがあります。
幼い子は不安を感じやすく「そばにいなくてごめん」と心を痛める看護師も少なくありません。
夜勤に行くときに子どもが泣いたり「ママ行かないで」と言われたりすると、仕事と割り切っていても心が揺れるものです。

パートナーの協力を得られない
共働きの家庭でも、夜間の育児や家事が一方に偏ると、負担は大きくなりがちです。
夜勤明けで疲れて家事や育児をこなすのはつらく、休む時間が取れません。
パートナーの理解や協力がないと「自分ばかり頑張っている」と感じ、つらさが増してしまいます。

迷惑をかけまいと無理な働き方をしてしまう
「休むと周りに迷惑がかかる」と無理をして働く看護師も少なくありません。
たとえば、子どもの体調が悪くても職場に気を遣って出勤してしまい、子どもと自分の体調を後回しにしてしまうこともあります。

看護師が子育てと夜勤を両立する4つの方法
看護師が子育てをしながら夜勤を続けるためには、次のような体力的・精神的な負担を軽減する工夫が必要です。
- 家族の協力を得る
- 院内保育・託児所を利用する
- 看護師長に相談して夜勤の回数を減らしてもらう
- 夜間保育・ベビーシッターを活用する
詳しく見ていきましょう。

1.家族の協力を得る
看護師が子育てと夜勤を両立するには、家族の協力は欠かせません。とくに、夜勤中や夜勤明けの時間帯は、パートナーや祖父母などの支援があることで、心身の負担を軽減できます。
たとえば、ある看護師は、夜間、どちらかが家にいられるようにパートナーと1か月分のスケジュールを調整し、家事や育児を分担して夜勤をしています。
このように、日頃から家族とよく話し合い、お互いのスケジュールや体調を考えることで無理なく子育てと夜勤を両立できるでしょう。

2.院内保育・託児所を利用する
院内保育所や24時間対応の託児所がある病院では、夜勤中でも子どもを預けられます。
勤務先の敷地内や近くで子どもを見てもらえるため、送り迎えがスムーズで、急な体調不良の呼び出しにもすぐに対応できます。また「すぐに駆けつけられる」と思えることで安心感にもつながるでしょう。
さらに、こうした保育施設の利用は「就労実績」として評価され、認可保育園の入園に有利になる場合もあります。まずは自分の勤務先にこうした施設があるかどうか、確認しておくと安心です。

3.看護師長に相談して夜勤の回数を減らしてもらう
子育てと両立しながら月に何回も夜勤に入るのがつらいと感じたら、夜勤の回数を減らしてもらうという方法もあります。
シフトの調整や働き方の柔軟性は、看護師長の理解と裁量に左右されやすいため、まずは現状の悩みや家庭の事情を正直に相談してみてください。
しっかり相談すると、育児と両立しやすい働き方を一緒に考えてもらえる可能性があります。無理のないシフトで長く働き続けるためのきっかけになるでしょう。

4.夜間保育・ベビーシッターを活用する
夜勤中に子どもを預ける手段として、夜間保育やベビーシッターの利用も有効です。
たとえば、東京都葛飾区では「ショートステイ・トワイライトステイ事業」「一時預かりベビーシッター利用支援事業」などの制度があり、24時間子どもを預けられたり、費用の一部を助成してもらえたりします。
こうしたサービスを活用できると、夜勤中も安心して働けるようになり、育児と両立しやすくなります。
自治体によってサービスや助成内容は異なるため、住んでいる地域にどのようなサポートがあるのか調べてみましょう。

看護師が子育てと夜勤の両立が難しいなら転職も検討
どうしても夜勤と子育ての両立が難しいと感じるなら、夜勤のない職場へ転職するのもひとつの方法です。
とくに、子育て中はライフステージに合わせて働き方を見直すことで、看護師を無理なく続けられます。
転職は、新しい働き方を見つけたり、自分のキャリアを考え直したりするチャンスにもなります。心や身体に負担をかけすぎる前に、自分に合った環境で安心して働ける道を探してみましょう。

看護師が子育て中でも働きやすい夜勤なしの職場
夜勤なしの職場は、育児との両立を目指す看護師にとって有効な選択肢です。
- 訪問看護ステーション
- クリニック
- デイサービス・デイケア
- 健診センター
- 一般企業
- 学校・保育園
これらの職場は、日勤中心で勤務が規則的であるため、子どもの生活リズムに合わせやすく、看護師の心身の負担も軽減できます。具体的な職場とその特徴を詳しく解説します。

訪問看護ステーション
訪問看護は日勤のみが基本で、利用者さまの自宅を訪問し、バイタルサインのチェックや点滴の投与などのケアをおこないます。直行直帰ができる職場もあり、家庭の事情に合わせて柔軟に働けるのが魅力です。
また、チームの情報共有や緊急時のサポート体制がしっかりしている職場を選ぶと安心です。
ただし、訪問看護ステーションの多くにはオンコール対応があります。オンコールの頻度や子育て中の看護師への配慮などは職場によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
訪問看護の働き方に興味がある方は、訪問看護に特化した求人を扱う「NsPaceCareer」をチェックしてみませんか。具体的な仕事内容や働き方の相談にもお答えします。訪問看護ステーションの働き方に興味がある方は、ぜひご活用ください。

クリニック
クリニックは、平日の日中に診療するところが多く夜勤がないため、子育て中の看護師にとって働きやすい職場です。クリニックでの業務は次のとおりで、病棟勤務に比べると緊急対応も少なめで落ち着いた環境で仕事ができます。
- 問診
- 採血や注射
- 医師の診察のサポート
勤務形態も柔軟で、午前のみや週3日から働けるパート勤務を選べるクリニックもあります。育児と両立しながら看護師の仕事を続けたい方には、クリニック勤務もひとつの選択肢としておすすめです。
関連記事:クリニック看護師の仕事内容4つ!診療科別の仕事内容とメリットを紹介

デイサービス・デイケア
デイサービスやデイケアは日勤のみで、残業もほとんどないため、家庭と両立しやすい職場です。
ここでの業務は、利用者さまとの会話や見守りが中心で、医療的な処置は比較的少ないため、子育て中の方のほかに、ブランクのある看護師も働きやすい環境です。
定時で退勤して保育園や幼稚園のお迎えにも間に合いやすい点は、子育て世代には安心材料になるでしょう。

健診センター
健診センターは、平日の日中勤務が基本で土日休みのケースが多く、子どもに負担をかけずに働けることが魅力です。おもな業務は次のとおりで、精神的な負担は少ない傾向です。
- 問診
- 採血
- 身体測定
接遇力や丁寧な対応が求められますが、毎日ほぼ決まったスケジュールで働けるため、育児に集中したい時期でも安定して勤務できるでしょう。

一般企業
産業看護師や企業の健康管理室で勤務する場合は土日祝が休み、夜勤なしで働けます。おもな業務は次のとおりで、突発的な対応が少なく、時間に追われにくいのが特徴です。
- 健康相談
- 体調管理
- 職場環境の衛生指導
生活リズムを整えやすく、育児と両立しながらスキルを活かせる職場のひとつであり、医療現場以外でのキャリアを築きたい看護師にも人気があります。

学校・保育園
学校の養護教諭や保育園の看護師として働く場合、春休みや夏休みなどの長期休みのときに休みを取りやすいため、家庭の予定とも合わせやすいのが魅力です。
仕事内容は子どもたちの健康管理や保健指導が中心で医療処置が少ないため、子育てとのバランスが取りやすい環境です。育児中でも無理なく働きたい方にぴったりの選択肢といえます。

子育て中の看護師の夜勤についてのよくある質問
子育てをしながら夜勤をする看護師が、疑問に感じやすいことを回答します。両立するためのヒントを得て、不安なく働きましょう。

Q1:看護師と子育ては夜勤があったら両立できないでしょうか?
夜勤をしても、子育てとの両立は十分にできます。
ただし、家族の協力や、夜間保育・ベビーシッターの活用などは欠かせません。職場が育児に理解のある環境かどうかも大切なポイントです。
自分の体調管理やこまめな休息、ストレスをためない工夫も意識してみてください。ひとりで頑張りすぎず、周りの力を借りながら、自分らしい働き方を見つけていきましょう。

Q2:看護師の夜勤は子どもが何歳から始めると良いですか?
一般的には、子どもが小学校に入る頃が夜勤を始める目安とされることが多い傾向です。
この時期になると、自分のことができるようになったり、看護師の仕事を理解してくれるようになったりすることが増えます。
ですが、子どもの性格や家庭のサポート状況によって、ベストなタイミングは人それぞれです。周りと比べず、家族のペースに合わせて無理のない形で考えていきましょう。

Q3:母親に夜勤があると子どもに影響しますか?
お母さんに夜勤があるからといって、子どもに悪い影響が出るというわけではありません。今のところ、はっきりした科学的な根拠もないとされています。
ただし、夜勤で子どもと過ごす時間が減ったり、子どもの生活リズムに影響したりすることはあるかもしれません。
夜勤明けやお休みの日に、子どもとふれあう時間を作り、毎日の生活リズムを整えることが大切です。

子育て中の看護師が夜勤をして後悔しないような働き方を実現しよう!
子育てをしながらの夜勤は、心も身体も負担になりがちです。
しかし、夜勤免除制度や病院独自の制度を活用することで、無理のないペースで働けます。
自分と家族の状況に合った働き方を見つけることが大切です。正しい情報を集めて、後悔のない働き方をしていきましょう。
<参考サイト・文献>
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | e-Gov 法令検索
ショートステイ・トワイライトステイ事業のご案内|葛飾区公式ホームページ
 NsPace Careerナビ 編集部
NsPace Careerナビ 編集部 「NsPace Career ナビ」は、訪問看護ステーションへの転職に特化した求人サイト「NsPace Career」が運営するメディアです。訪問看護業界へのキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。