看護におけるリスクマネジメントとは?看護師の役割と事例をもとに解説
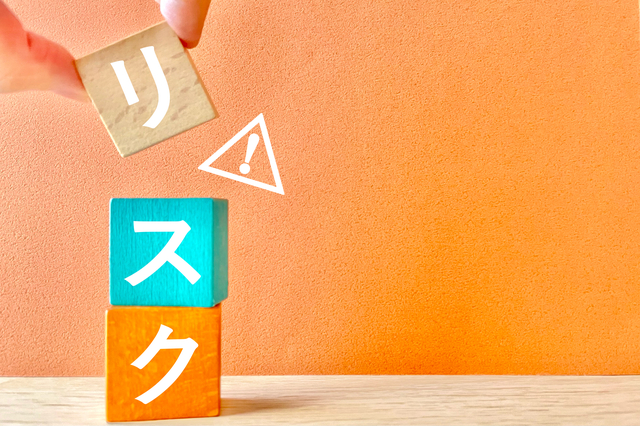
「看護におけるリスクマネジメントって何?」「多忙な現場で事故を起こさないように気をつけるためには何をすれば良いの?」
看護の現場では、ヒューマンエラーが重大な事故につながる恐れがあります。特に、患者さまとの接触が多い看護師は、リスクを予測し、事故を未然に防ぐための対策を日常的に求められます。
この記事では、看護におけるリスクマネジメントの定義や現場で発生しやすいトラブルの実例を挙げ、実践できるマネジメント手法を紹介します。自信を持ってリスク対策に取り組めるようになり、職場の安全意識を高められるでしょう。

看護におけるリスクマネジメントとは?
看護におけるリスクマネジメントとは「施設の関連部門と連携しながら、患者さまやご家族、スタッフの安全を守り、危険を回避すること」です。看護の現場では、次のようなリスクが起こる可能性があります。
- 転倒・転落
- 誤薬
- 患者さまの誤認
- 針刺し事故
看護師は、ベッドサイドでケアする機会が多く、患者さまの変化をいち早く察知できる立場にいます。そのため、リスクマネジメントを担う重要な役割があります。

看護の現場で発生しやすいトラブルのリスク
多忙な看護の現場は、ヒューマンエラーが発生しやすい環境にあります。実際に、日本医療機能評価機構2024年の「医療事故情報収集等事業」では、報告された3万2,034件のうち、2万2,305件が看護業務に関連するものでした。ここでは、医療事故につながりやすい代表的なリスク要因を挙げます。
- 多忙な勤務による確認不足
- 人手不足によるケアの遅れ
- 情報共有の遅れや申し送りミス
- 夜勤帯の少人数体制による見落とし
- 長時間勤務による疲労と集中力の低下
これらのリスクは、複数の要因が絡み合うことで、重大な医療事故へと発展しやすくなります。組織でこれらの問題を把握し、対策を講じることが重要です。

多忙な勤務による確認不足
業務量の多さは、確認手順の省略というリスクを生みます。業務に追われることで、「毎回やらなくても大丈夫だろう」「今は忙しいから後でしっかり確認しよう」という手順の省略が発生し、ヒューマンエラーの確率が高まるのです。
たとえば、内服薬を渡す際に、患者さまの名前確認のダブルチェックを省略したり、投薬する前のバーコード認証を怠ったりすることが、重大なミスにつながる危険性があります。

人手不足によるケアの遅れ
慢性的な人手不足は、必要なケアを時間通りに提供できないというリスクを招きます。スタッフが不足していると、業務に優先順位をつけざるを得なくなり、予防的なケアの間隔が空いてしまうからです。
本来、2時間おきにおこなうべき体位交換や巡視の間隔が空くことで、褥瘡(床ずれ)や転倒・転落の発生といったリスクの増大につながります。
人手不足は、ケアの質そのものを低下させると同時に、事故が起こるリスクを高める深刻な問題です。

情報共有の遅れや申し送りミス
情報伝達の不備は、不適切な医療行為につながる恐れがあります。患者さまの状態や指示変更の情報が、正確に共有されなかった場合、看護師の介入の遅れや誤った判断を招くからです。
- 情報の伝達漏れ:鎮痛剤の増量指示が申し送りで伝わらず、患者さまが痛みに耐えることになった
- 状態変化の見落とし:患者さまに微熱と咳があったが、申し送りを怠った結果、肺炎が悪化した
- 情報の共有不足:薬剤アレルギー歴がカルテ上に記載されておらず、アレルギー反応を起こす危険性のある薬剤を処方した
次の担当者への申し送りで伝わらなかった場合、治療の遅れや不適切なケアにつながるなど、患者さまに悪影響を及ぼす可能性があります。

夜勤帯の少人数体制による見落とし
夜勤帯は、限られたスタッフ数で複数の患者を対応する必要があり、観察の目が行き届きにくくなることで、患者さまの初期の異常や軽微な変化を見逃すリスクが高まります。
また、日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」では、交代制勤務や夜勤によって注意力・判断力の低下、睡眠の質の悪化が生じやすく、それが医療の安全性に影響する可能性があると指摘されています。
そのため、夜勤体制の見直しや、夜間の業務負担を軽減する取り組みが、リスクマネジメントの観点から重要です。

長時間勤務による疲労と集中力の低下
看護師の長時間労働は、判断力と集中力の低下を招き、エラー率を上げます。疲れが溜まっている状態では、冷静な状況判断や正確な手技が難しくなるためです。
たとえば、疲労による集中力の低下によって、薬剤の投与時間の計算ミスや患者間違いを誘発したり、緊急時に適切な対応手順を思い出せなくなったりするかもしれません。
疲労は安全を脅かす要因であるため、これを放置すると、重大な医療事故の発生リスクが上がります。

看護の現場で起こりやすいリスクの事例
ここでは、看護の現場で起こりやすいリスクの事例を3つご紹介します。
- 転倒・転落
- 投薬ミス
- 患者さまの誤認
これらの事例は、発生頻度が高く、患者さまに重大な影響を及ぼしやすいものです。リスクマネジメントにおいては、ヒヤリ・ハット報告を通じて、これらの事例がなぜ発生したのか原因を分析し、対策を講じる必要があります。

転倒・転落
| 70代女性(認知症、左片麻痺、転倒歴あり)の事例。 離床センサー作動後、看護師がすぐに訪室したものの、すでに病室の床に倒れていた。「立ったら倒れた」とのことで、右額をオーバーテーブルの脚にぶつけたが外傷は軽微だった。入院時より頻尿で離床が多く、離床センサーが頻繁に作動。履物を履かず靴下で移動していたこと、看護師が離床直後の動きを十分に観察できていなかったことが発生要因とされた。 |
この事例は、麻痺や認知症、頻尿といった患者側のリスクに加え、危険行動(靴下での歩行)と看護師の観察不足が重なったことで発生したと考えられます。離床センサーが頻回に作動していることから、訪室する回数を増やしたり、ベッド周囲の物品を整理したりする対策が必要です。また、看護師の目が届きやすい病室に移動するといった対応が求められます。

投薬ミス
| 70代の男性患者(狭心症のため冠動脈造影検査予定)の事例。 朝の検査準備中に「今、夕方の薬も一緒に飲んでしまった」と患者さまから看護師に報告。本来、朝1錠内服予定だった硝酸イソソルビド錠20mgを、朝夕の2錠分まとめて服用していたことが判明した。前日夜勤の看護師が朝の分を配薬ケースに入れ説明したものの、夕方分の薬袋も同時に本人に渡してしまっていた。 |
この事例は、患者さまへの説明が不十分であり、薬剤の管理方法が不適切であったため発生した可能性があります。事故を防ぐためには、患者さまが薬剤を管理できるのかアセスメントしたうえで、薬剤を渡すタイミングを決めなければなりません。とくに、患者さまが検査を受けることに不安や緊張を感じている場合、普段とは異なる心理状況にあるため、その都度手渡しするといった方法に変えることで事故を防げるでしょう。

患者さまの誤認
| 心電図モニターをつけ間違えた事例。 看護師Aは、患者Xと患者Yを受け持っていた。患者Xは術後1日目で心電図モニター装着の指示が出ていた。患者Yは、既往に心房細動があったことから、心電図モニターを装着することになった。看護師Aと先輩看護師Bは、セントラルモニタで入床の設定をする際、2人分の送信機とセントラルモニタをダブルチェックした。その後、看護師Aは、誤ってそれぞれ逆の送信機を装着した。夜勤の看護師Cが間違いを発見した。 |
この事例は、セントラルモニタ側のチェックだけでなく、ベッドサイドでの最終的な患者と機器の紐付け確認が疎かになったことで発生した恐れがあります。ベッドサイドでもダブルチェックしたり、装着後も心電図の波形が正しく表示されているのかを確認したりすることが、心電図モニターの装着間違いを防ぐためには重要です。
関連記事:【事例別】看護師が起こしやすいインシデントと予防策!立ち直れないときの対処法

看護師が実践できるリスクマネジメントの方法
リスクマネジメントは、リスクマネージャーや管理職だけがおこなうものではありません。業務のなかで看護師が意識し、実践できる具体的な方法を解説します。
- 危険予知トレーニング(KYT)の実施
- 5S活動の推進
- マニュアルの作成
- インシデント報告書の活用と再発防止策の検討
- リスクマネジメント研修への参加
これらの手法を実践することで、看護師の危険を察知する感度が高まり、ケアの質と患者さまの安全を守ることにつながるでしょう。

危険予知トレーニング(KYT)の実施
危険予知トレーニングを実施することで、チームの危険に対する感度を高められます。
事例をもとに「自分の職場の、この業務の、この瞬間に」などの危険性をイメージしながら、話し合うことで、同じような事例に遭遇したときに事故発生を予防できるからです。
たとえば、配薬するときに「どのような危険が潜んでいるか?」をチームで共有し、「どうすれば安全か」を確認し合います。
危険予知トレーニングは、事故を防ぐための気づきと共有を習慣化し、リスクマネジメントをチームで推進するうえで有効です。

5S活動の推進
5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動は、環境要因によるミスを根本から減らすためのリスク対策です。物品や情報が整理されることで、誤った物品を使用するリスクや、探すことによる焦りを防げるからです。
- 薬剤カートには似た名前の薬を離して配置する
- 使用期限のチェックをルーティン化する
- 定位置に戻す習慣を徹底する
5S活動を進めることは、作業効率と安全性を向上させ、ヒューマンエラーが発生しにくい職場環境を作ります。

マニュアルの作成
業務の手順を標準化するマニュアルの作成・更新は、スタッフ間のケアのバラつきや、ミスを防ぐために重要です。スタッフ間で手順の認識が異なると、交代時や応援時にエラーが発生しやすくなります。
緊急時の対応手順や輸血開始前のチェックなどリスクの高い業務について、誰がやっても同じ結果になるように手順を統一する必要があります。
また、マニュアルは一度完成させたら終わりではありません。定期的に内容を見直し、周知徹底することで、看護ケアの質と安全性の向上につながります。

インシデント報告書の活用と再発防止策の検討
インシデント報告書は「なぜそのミスが起こったのか」を分析することで、看護師が実践しやすい再発防止策を検討するために活用すべきです。
たとえば「残業で疲れていたため、投薬時に患者さまの名前を読み上げなかった」という報告に対し確認の徹底だけでなく「残業時間の是正」や「休憩時間の確保」など労働環境の改善を組織で検討しなければなりません。
インシデント報告書は、事故の芽を摘み、組織の安全システムを改善するためのPDCAサイクルを回す出発点として重要です。

リスクマネジメント研修への参加
リスクマネジメント研修への参加は、看護師の知識をアップデートし、安全意識を維持するために不可欠です。研修は、最新の医療安全の考え方や他施設の事例を学び、現場に取り入れる機会となるからです。
一例として、医療安全管理者が主催するセミナーや学会に参加して、最新のガイドラインやリスク分析手法など学んだことを病棟で伝えてください。研修参加を通じて知識を共有することで、病院の安全への意識を高められるでしょう。

看護におけるリスクマネジメントについてのよくある質問
ここでは、看護師としてリスクマネジメントに取り組むうえで、キャリアや制度について、よく寄せられる質問にお答えします。

Q1:新人看護師でもリスクマネジメント研修に参加できますか?
多くの医療機関では、新人看護師もリスクマネジメント研修に参加することができます。配属後まもなく実施されるケースもあり、まずは所属施設の研修制度を確認してみるとよいでしょう。
新人のうちは業務に不慣れなため、ヒヤリ・ハットに直面する場面も少なくありませんが、早い段階でリスクに対する意識を育むことは、自身の安全を守り、質の高い看護ケアを提供する第一歩となります。

Q2:ヒヤリ・ハット事例で報告件数が多い事例は何ですか?
ヒヤリ・ハット事例の報告件数の割合を次の表にまとめました。
| 事例の概要 | 割合 |
| 薬剤 | 35.0% |
| 療養上の世話 | 21.9% |
| ドレーン・チューブ | 13.8% |
| 検査 | 8.6% |
| 治療・処置 | 4.8% |
| 医療機器等 | 4.0% |
| 輸血 | 0.5% |
| その他 | 11.6% |
すべての事例が看護師からの報告というわけではありませんが、薬剤や療養上の世話、ドレーン・チューブの割合が高くなっています。これらは看護師の業務にかかわるため、重点的なリスク対策と確認手順の徹底が必要であることがわかります。
関連記事:看護師は保険に入るべき?検討すべき5つの理由と看護師賠償責任保険制度を解説

Q3:リスクマネージャーになるには資格は必要ですか?
リスクマネージャーには必須の国家資格はありませんが、特定の資格取得や研修の受講が求められることがあります。
たとえば、日本看護協会主催の「医療安全管理者養成研修」の受講がリスクマネージャーの要件とされる場合があります。実務経験と、組織全体の改善に取り組むリーダーシップが重要です。

看護におけるリスクマネジメントとは安全を守り危険を回避すること!
看護におけるリスクマネジメントは、業務に潜む危険を予知し、患者さまやご家族、看護師の安全を守るために不可欠です。
多忙な環境下であっても、危険予知トレーニングや5S活動、インシデント報告の検証といった手法を意識的に実践することで、事故発生のリスクを減らせます。看護師一人ひとりがリスクへの感度を高めることが、安全で質の高い看護の実現につながります。
NsPaceCareerでは、「ひとり訪問でも、安心して看護に集中できる」——そんな医療安全の体制が整った訪問看護ステーションの求人をご紹介しています。
あなたの安全意識が、利用者さまの安心につながる職場を一緒に見つけてみませんか?
<参考サイト・文献>
ヒヤリ・ハット事例|日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業
ヒヤリ・ハット事例|日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業
 NsPace Careerナビ 編集部
NsPace Careerナビ 編集部 「NsPace Career ナビ」は、訪問看護ステーションへの転職に特化した求人サイト「NsPace Career」が運営するメディアです。訪問看護業界へのキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。


















