現役看護師の勉強方法まとめ5選!忙しくても続けられるコツも紹介
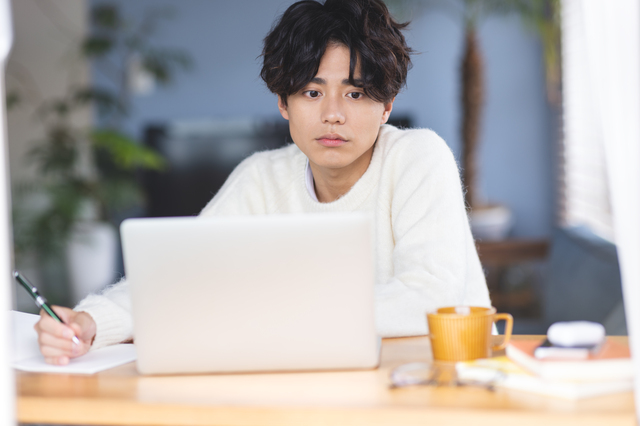
「スキルアップしたいけれど、何から始めれば良いか分からない」「仕事が忙しくても勉強を続けられる方法は?」──そう感じている看護師の方も多いのではないでしょうか。
夜勤や残業で忙しい看護師にとって、勉強時間の確保は簡単ではありません。しかし、質の高いケアを提供し、自分のキャリアを高めるためには、日々の学びが欠かせません。
本記事では、現役看護師がスキマ時間でも無理なく実践できる勉強方法を5つ紹介し、それを継続するための具体的なコツも解説します。

現役看護師の勉強方法まとめ5選
日本看護協会では、「看護職の生涯学習ガイドライン」の中で、国民の健康を支えるために看護職は生涯にわたり学び続ける必要があるとしています。ここでは、現役看護師が業務で忙しい状況でも学習を継続でき、知識や技術を深められる勉強方法を紹介します。
- アプリや音声学習を活用する
- 実際の症例と結びつけて知識を深める
- 後輩や同僚に共有する
- 学会やセミナーに参加する
- 資格試験用のテキストを参考にする
それぞれの方法を確認して、自分に合った方法を取り入れてみてください。

アプリや音声学習を活用する
アプリや音声学習を活用すると、通勤中や家事の合間などスキマ時間を使って効率的に勉強できます。
たとえば、通勤電車の中で音声を聞き流したり、料理をしながらイヤホンで専門知識の解説を聞いたりできます。テキストを開く時間や場所がない場合でも、この方法であれば知識を積み重ねられるでしょう。

実際の症例と結びつけて知識を深める
実際の症例と結びつけて知識を深めると、学んだ内容が現場でどう役立つかイメージできるため、記憶に残りやすくなります。
「患者さまの心不全の悪化は、なぜ起きたのか」という疑問をもとにガイドラインや専門書を確認します。実際のケースと結びつけることで「あのとき、この知識があれば、より良いアセスメントができた」と具体的に考えられるようになるのです。
また、先輩から指導してもらったことをもとに担当した患者さまの病態や治療経過を振り返ると、現場ですぐに活かせる知識として定着し、業務の取り組み方も変わります。

後輩や同僚に共有する
後輩や同僚に共有すると、自分の理解度を試せるだけでなく、教える過程で知識が整理され定着します。学んだ知識やスキルを、カンファレンスや休憩時間などに後輩や同僚へ説明してみてください。
曖昧な部分を明らかにする必要があるため「この手順ってどうだったかな?」と疑問点がはっきりとして調べ直す機会にもなるのです。さらに、教えた相手からの質問に答えることで、知識を深められるでしょう。

学会やセミナーに参加する
学会やセミナーに参加すると、最新の医療情報や知識を学べ、モチベーションの維持にもつながります。
職場でよく担当する病気に関連するセミナーに参加すると、最先端の治療法やケアの動向を学べます。学会では、講演だけではなく企業ブースや展示もあり、幅広い視点で学びを深めることができます。また、ほかの看護師との交流の場にもなるため、仕事への刺激を受けたり、新たな人脈を作ったりする機会になるでしょう。

資格試験用のテキストを参考にする
資格試験用のテキストを参考にすると、専門分野の知識を効率良く学べます。
たとえば、救命救急センターや集中治療室の分野で知識を深めたいなら、集中ケア認定看護師教育課程のテキストを使いましょう。このテキストには、重要な知識がまとめられているため、何から手をつければ良いかわからない方におすすめです。
試験を受ける目的がなくても、テキストを使って学習するだけで、質の高い知識を身につけられます。テキストは必ず最新版であることを確認しましょう。

キャリア別の現役看護師の勉強方法
看護師のキャリアによって、必要な知識や勉強の焦点は異なります。それぞれの段階に合った勉強方法を紹介します。
- 新人看護師
- 中堅看護師
- ベテラン看護師
- ブランクがある看護師
新人からベテランまで、それぞれに求められる知識と、身につけるためのアプローチを見ていきましょう。

新人看護師
新人看護師は、学生時代に学んだ知識と実際の臨床現場を結びつけることが重要であるため、まず基礎的な看護技術と知識を確実にする勉強に集中しましょう。
たとえば、導尿の手順を学習する場合、なぜその手順でおこなうのか根拠を確認したり、対象者の病態生理や注意点などを優先的に勉強したりします。この段階で基礎を固めることが、今後の応用力を高める土台となるのです。

中堅看護師
臨床経験を積み、業務に慣れてきた中堅看護師は、自分の興味や部署のニーズにもとづいて専門分野を深掘りしましょう。
たとえば、糖尿病を持つ患者さまが多い部署なら、糖尿病療養指導士の知識を学んだり、自己注射の指導のポイントをまとめたりします。後輩への指導時に、根拠にもとづいた説明ができるように、自分の知識をアップデートする必要があります。

ベテラン看護師
長年の経験と知識があるベテラン看護師は、これまでの自分の経験則と最新のエビデンスを比較・統合する勉強がおすすめです。
たとえば、疾患の治療ガイドラインが更新されていないかを確認し、自分のケアが最新の知見に沿っているかを検証します。また、マネジメントや教育に関心がある場合は、医療安全やリスク管理、組織論などの分野を学ぶことも有効です。
知識を更新し続けることは、質の高いケアを継続し、若い世代の模範となるために不可欠です。

ブランクがある看護師
ブランクがある看護師は、まず基本的な看護技術と、最新の医療知識やケアを再確認する勉強をしてください。これまでの知識や技術が通用するかという不安を解消することが大切です。
たとえば、輸液ポンプやシリンジポンプなどの医療機器が新しくなったことにともない、操作方法が変更されている可能性があるため、動画やテキストで確認しましょう。また、感染対策の最新のガイドラインも振り返ることで、実態に沿った対策ができます。
ナースプラザで実施している復職支援研修に参加することで、新しい知識を学び、現場で働く自信を取り戻せるでしょう。ブランクから復帰を考えている方は、下記の記事で詳しく解説しているため、一度ご覧ください。
関連記事:看護師の勉強をやり直したい!勉強方法5選とブランクがあっても復職しやすい職場

現役看護師が直面する勉強の課題
現役看護師が勉強しようとする際に、共通して直面する課題と、それに対する考え方を紹介します。
- 夜勤や残業でまとまった時間が取れない
- 国家試験以来、勉強習慣が途切れている
- どの教材から手をつけていいかわからない
- 勉強しても成果が見えにくい
- 疲れてモチベーションが続かない
現役看護師が勉強を継続するうえで、時間不足やモチベーションの維持など、さまざまな壁にぶつかります。これらの課題を乗り越えるための具体的な対策と、考え方を変えるヒントを見ていきましょう。

夜勤や残業でまとまった時間が取れない
現役看護師の方は、夜勤や残業で不規則な勤務形態である場合、まとまった時間を確保することが難しいことが課題です。
看護師の仕事は日勤や夜勤、遅出など勤務時間が流動的であり、身体的にも精神的にも疲労が溜まりやすいからです。そのため「毎日この時間に勉強する」といった固定的な計画を立てても、仕事の状況で崩れがちです。勉強の計画を立てるのが難しく、学習を続けるきっかけを失うかもしれません。

国家試験以来、勉強習慣が途切れている
国家試験の合格後は勉強の目的や強制力がなくなるため、業務以外での学習習慣が途切れてしまうことが課題です。学生時代は国家試験というゴールがありましたが、臨床現場に出てからは学習が個人の意思次第になりがちです。
参考までに、総務省「令和3年社会生活基本調査」によると、15歳以上のうち「学習・自己啓発・訓練」をしている人の割合は38.8%です。看護師に限らず、社会人はさまざま理由から学習し続けることが難しいといえます。
また、業務が忙しいと「疲れたから明日にしよう」と先延ばしになり、途切れた勉強習慣を再開させるのが困難になります。

どの教材から手をつけていいかわからない
現役看護師が勉強する課題は、専門分野や教材の種類の多さから、何を優先して学ぶべきかわからないことです。
とくに、新しい分野を学び始めるとき「どの知識が現場で本当に役立つのか」という判断が難しくなり、教材選びだけで時間とエネルギーを消費してしまうこともあるでしょう。結果、実際の学習がなかなか始まらないという状況に陥るかもしれません。

勉強しても成果が見えにくい
努力しているにもかかわらず、自分の知識がどの程度身についているのか成果が見えにくいことが、学習を継続するうえでの課題になりがちです。
日々の学習を点数や合格という形で評価する機会がないため「本当に知識が定着しているのだろうか」という不安を感じやすくなります。この不安感は、勉強への意欲を低下させる要因になります。

疲れてモチベーションが続かない
看護師の仕事は身体的・精神的な消耗が激しいため、疲労が溜まると勉強に取り組むためのエネルギーが残らないことが課題のひとつです。
夜勤や残業が続くと、休息を優先する必要があり、勉強を始められない人もいます。「勉強しなければ」というプレッシャーがきっかけで、学習から離れるという悪循環に陥ることも少なくありません。
関連記事:看護師が激務といわれる3つの理由!辞めたいときは訪問看護師も一手

現役看護師が忙しくても勉強を続けるコツ
忙しい現役看護師が、モチベーションを維持しながら、無理なく勉強を継続するための具体的なコツを紹介します。
- 勉強を続ける目標を明らかにする
- 通勤時間を活用する
- 実際の症例に活かせる内容を勉強する
- 同僚や友人と一緒に学ぶ
- 勤務中のスキマ時間を活用する
モチベーションを保ちながら学習を続けるための具体的な方法を見ていきましょう。

勉強を続ける目標を明らかにする
勉強を続けるには、何のために学ぶのかを具体的にすることが大切です。目的がはっきりすると、途中で挫折しにくくなりやる気を保てます。
たとえば「スキルアップしたい」という漠然とした目標ではなく「来年の認知症ケア専門士の試験に合格する」「3年以内に緩和ケア認定看護師の資格を取る」といった形で、達成時期と内容を明らかにしましょう。
目標が具体的であるほど、やるべき勉強がはっきりとするため、計画的に学習を続けられます。

通勤時間を活用する
通勤時間を活用することも、現役看護師が勉強を続けるコツです。日々の生活リズムを変えずに、勉強時間を確保できます。
たとえば、電車やバスでの移動中に、電子書籍で専門書を読む、音声学習アプリで講義を聞くといった方法があります。
片道30分の通勤時間があれば、往復で1時間の勉強時間を確保できます。毎日の習慣に組み込めるため、無理なく勉強を続けやすいでしょう。

実際の症例に活かせる内容を勉強する
今の仕事に直結する内容を勉強すると、やる気が出やすく覚えやすくなります。
「担当している患者さまの病気をもっと知りたい」と思ったら、そこから勉強を始めます。呼吸器の患者さまなら、呼吸器の解剖生理や酸素療法の理由を重点的に学ぶイメージです。
勉強したことがすぐにケアに使えるため「学んでよかった」と実感しやすいです。達成感が得られることで、次の勉強にもつながるでしょう。

同僚や友人と一緒に学ぶ
同僚や友人と一緒に学ぶと励まし合い、モチベーションを維持しやすくなります。
たとえば、月に一度「お互いに教え合う会」を開くと、1人で黙々と勉強するよりも楽しく取り組めるでしょう。「みんなも頑張っている」という安心感を得られ、わからない点を教え合うことで理解も深まります。

勤務中のスキマ時間を活用する
勤務中のスキマ時間を活用すると、仕事の延長線上で勉強できるため、無理なく知識を深められます。
たとえば、はじめて見た疾患の情報をスマートフォンで検索したり、メモを見返してその日の振り返りをしたりする方法です。場所を変えずにすぐに勉強できるため、習慣化しやすいのがメリットです。
ただし、勤務中や職場でのスマートフォンの使用を制限している場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

現役看護師の勉強方法についてのよくある質問
現役看護師が抱えやすい勉強についての疑問にお答えします。

Q1:勉強内容は基礎から学び直すべきですか?応用からでも大丈夫ですか?
勉強する内容によって異なりますが、基礎知識に不安があるなら、まずは基礎から学び直すことをおすすめします。基礎知識がしっかりないまま応用的な内容を学んでも、根本的な理解が難しくなり、知識が定着しにくいからです。
基礎を固めておくと、応用的な内容を学んだときに「なぜそうなるのか」という理解がスムーズになります。
まずは解剖生理や薬理作用など、患者さまの状態をアセスメントするために欠かせない部分をテキストで確認しましょう。

Q2:勉強の効果を実感するにはどうすれば良いですか?
勉強した知識を、看護実践で意識的に使ってみると、勉強の効果を実感できます。自分の言葉で記録に残したり、患者さまへのケアの根拠として活用したりしましょう。
たとえば、新しい褥瘡の評価方法を学んだら、実際に患者さまの褥瘡を評価してみます。現場で「役に立った」と感じられると、知識が身についた実感が得られ、勉強の成果を感じやすくなります。

Q3:忙しくて勉強のモチベーションが続かないときはどうすれば良いですか?
やる気が落ちたときは、まずは勉強する目標を振り返ることが大切です。
「なぜ勉強を始めたのか」「どのような目標があるのか」を思い出しましょう。そのうえで「少しでも進めば十分」と割り切り、まずは5分だけやってみるのも効果的です。寝る前に1日たった5分だけの勉強でも、5分×週5日実施することで、1週間で約25分勉強したことになります。小さな一歩を積み重ねることで、またモチベーションが戻ってくるはずです。

現役看護師は勉強方法を押さえてキャリアアップしよう!
アプリやオンライン学習などを活用し、実際の症例と結びつけて知識を深めるなど、自分に合った勉強方法を見つけて、今日から実践しましょう。
忙しいときでも、毎日知識を積み重ねていくことが、質の高い看護につながります。また、看護師としてのキャリアをより豊かにするでしょう。
専門性の高い分野での活躍を考えているなら、NsPaceCareer(訪問看護師に特化した求人サイト)をぜひご覧ください。訪問看護師の求人を豊富に扱っています。自分のペースで専門性を磨きたい方や、新しい環境で挑戦したい方にとって訪問看護は学びの深い領域です。現役の訪問看護師への無料相談も受けつけているため、お気軽にご利用ください。
<参考サイト・文献>
 NsPace Careerナビ 編集部
NsPace Careerナビ 編集部 「NsPace Career ナビ」は、訪問看護ステーションへの転職に特化した求人サイト「NsPace Career」が運営するメディアです。訪問看護業界へのキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。


















